そこで本記事では、誤解が生じやすいポイントを中心に、免税(ゼロ税率)と非課税の違いを補足しました。
※以下は、以前公開した記事を状況に合わせて加筆・修正したものです。
和歌山の税理士・和田全史です。
以前、「消費税が下がったら、事業者にはどんな影響がある?」というコラムを書きました。そのときは、消費税率の引下げや軽減税率の拡大といった話が再浮上していた時期でしたが、今回はそれよりも踏み込んだ内容が出てきました。
自民党と日本維新の会の連立政権合意書の中で、「飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としないことも視野に法制化を検討する」という方針が示されたのです。
もし実現すれば、家計にとっても事業者にとっても大きな転換点となります。今回は、その内容と実務上の影響について整理してみたいと思います。
「飲食料品は消費税の対象としない」――連立合意書に示された新方針
連立政権合意書には、「飲食料品は消費税の対象としない」ことを二年間に限って視野に入れ、法制化の検討を行う旨が明記されました。もっとも、この「対象としない」という表現は、消費税法上の用語である「非課税」や「免税(ゼロ税率)」を直ちに指すものではなく、現時点ではどちらの制度を想定しているか不明確です。
仮に「非課税」とされた場合、仕入税額控除ができないため、飲食料品を取り扱う製造・流通・小売業にとって負担が増えることが考えられます。結果として販売価格は上昇しやすく、家計支援効果は限定的になり得ます。一方、「免税(ゼロ税率)」であれば、事業者の仕入税額控除を維持しつつ価格を据え置きやすく、家計支援の観点からも運用上はより現実的です。どの方式を採るかによって影響は大きく異なるため、今後の法案段階での設計を注視する必要があります。
「非課税」と「免税(ゼロ税率)」の違いを整理しておく
消費税法上の「非課税」と「免税(ゼロ税率)」は、いずれも消費税が課されない点では同じですが、仕組みと実務上の影響は大きく異なります。
「非課税取引」とされるのは、土地の譲渡・貸付をはじめ、医療や教育、住宅の賃貸などです。これらは、課税の対象としてなじまない取引や、社会政策的配慮により非課税とされています。
非課税取引では、消費税を受領することはありませんが、その売上を得るために経費を支払う際には、通常どおり消費税を負担します。ただし、非課税売上に対応する仕入税額控除は認められないため、経費に含まれる消費税が事業者の負担として残り、いわゆる「損税」となります。
一方、「免税(ゼロ税率)」は課税取引の一種で、税率を0%とする仕組みです(代表例:輸出)。売上に消費税はかかりませんが、経費に含まれる消費税は控除できます。したがって、経費段階で支払った消費税がコストにならず、価格を上げずに済む点で、事業者・消費者双方の実質的負担が小さい制度といえます。
今回の「飲食料品は消費税の対象としない」という表現がどちらを想定しているかは不明ですが、家計支援を目的とするなら、仕入税額控除を維持できる「免税(ゼロ税率)」方式の方が現実的と考えられます。
免税方式が導入された場合の実務的影響――2年間の時限措置をどう備えるか
免税(ゼロ税率)方式が導入されれば、消費者から見れば単純に「価格が下がって助かる」という話ですが、事業者にとってはもう少し複雑です。
まず、免税取引はあくまで「課税取引の一種」とされます。したがって、売上の税率に0%の区分を新たに追加する必要があります。特に複数の税率を扱う小売店や飲食店などでは、レジや会計システムの設定変更が避けられません。
さらに、今回の措置は「2年間の時限的な制度」とされています。つまり、制度導入時だけでなく、2年後に元の税率へ戻す作業も発生します。システムや価格表示、商品マスタなどを2度変更する必要があり、導入と廃止の両方にコストがかかる点が大きな負担となります。
このような制度変更には、過去にも似た前例があります。2019年に軽減税率制度が導入された際には、レジや会計ソフトの改修を支援する「軽減税率対策補助金」が設けられました。今回も同様の補助措置が検討される可能性はありますが、制度設計の詳細や予算措置が遅れると、現場の準備期間が限られるおそれがあります。
もっとも、政府としては物価上昇による家計負担への対応を急いでおり、できるだけ早期に実施したい考えのようです。ただ、短期間でこうした複雑な制度を設計し、現場が混乱なく対応できるのかは、慎重に見極める必要があります。
免税方式が正式に導入される場合、準備期間や支援策の内容によって現場の負担は大きく変わります。短期間での制度入れ替えは混乱を招きやすいため、事業者としては早めに情報収集を行い、対応の方向性を検討しておくことが重要です。
まとめ
今回の連立政権合意書で示された「飲食料品を消費税の対象としない」という方針は、家計支援の観点からは大きなインパクトがありますが、実務面では多くの課題を伴います。
ただ、合意書にある「消費税の対象としないことも視野に、法制化の検討を行う」という表現は、実のところ何も確定していません。制度の導入が決まったわけではなく、あくまで「検討を始める」という段階にすぎません。
そのため、現時点では制度の方向性を断定することはできませんが、もし実現する場合には、2年間という時限措置である以上、導入・廃止の双方にコストと手間が生じることは避けられません。制度の動向を注視しつつ、早めの情報収集と準備が求められます。
次回は、もし免税(ゼロ税率)方式が導入された場合に、税額計算がどのように変わるのか――本則課税・簡易課税の違いを踏まえながら、具体的に整理してみたいと思います。

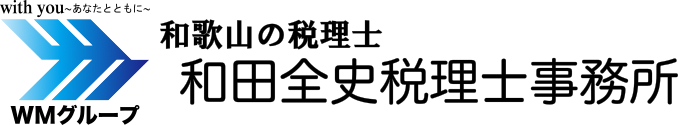
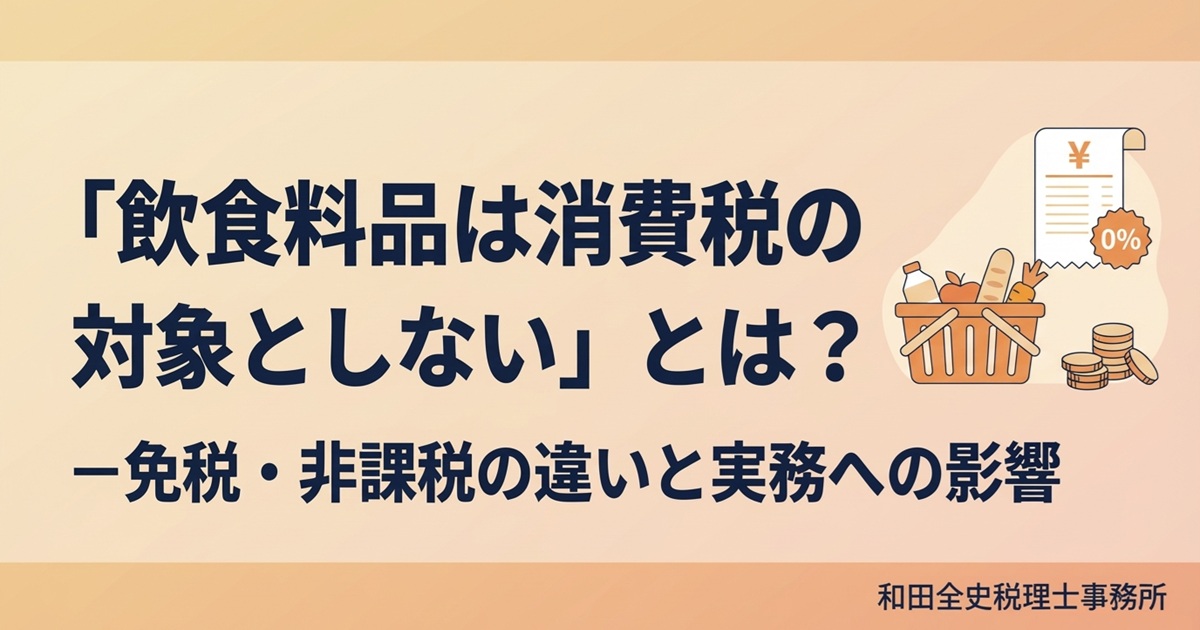
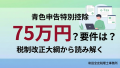

コメント