和歌山の税理士、和田全史です。今回もブログをご覧いただきありがとうございます。今回から「年収の壁総整理」と題して、数回に分けて整理してみたいと思います。まず第1回は「年収の壁はなぜ問題になるのか?」というお話です。
「年収の壁」とは何か?
「年収の壁」とは、働く人の収入がある基準を超えたときに、税金や社会保険料の負担が急に増える、または扶養の対象から外れてしまうことで、結果的に世帯全体の手取りが減ってしまう現象を指しています。
大きく分けると、次の3つの側面があります。
- 本人の税金 ― 一定の収入を超えると、まず住民税がかかり、その後は所得税も課税されるようになります。
- 扶養者(主に配偶者や親)の税金 ― 本人の収入が増えることで、配偶者控除や扶養控除の対象から外れ、配偶者や親の税負担が増えることがあります。
- 本人の社会保険料 ― 社会保険の扶養から外れると、本人が自分で健康保険や年金の保険料を負担することになります。世帯全体の手取りが減る大きな要因です。
つまり「年収の壁」は、本人だけの話ではなく、世帯全体に影響するのが特徴です。少し収入が増えただけで「働き損」と言われるのは、このためです。
壁が生じる背景
「年収の壁」と呼ばれるのは、基準をわずかでも超えると負担が急に増える制度があるからです。
代表的なのは 住民税の非課税限度額 や 扶養控除 です。これらは1円でも超えると一気に条件が変わり、税負担が増えてしまいます。典型的な“崖”のような仕組みです。
一方で、すべてが崖のような制度ではありません。
- 配偶者控除 は、配偶者特別控除があるため、少し超えた程度なら控除額が段階的に減る仕組みになっています。
- 社会保険 は、130万円や106万円といった基準がありますが、年収ベースで判断されるため、単月で少し超えただけでは直ちに扶養から外れることはありません。ただし、継続的に超えると本人が保険料を負担することになります。
このように「崖のように一気に不利益が出る制度」と「緩やかに変わる制度」が混在しているため、とても分かりにくいのが実情です。それでも多くの人が「壁」を気にするのは、やはり少し収入が増えただけで手取りが減る不安が強いからだと思います。
なぜ問題になるのか?
年収の壁が問題になるのは、税金や社会保険料の負担が増えること自体よりも、それが働き方や世帯の暮らし方に大きな影響を与えてしまうからです。
- 就労調整の発生 ― 「壁を超えると損をする」と考えて、労働時間や収入をあえて抑える人が多くなります。本来ならもっと働けるはずなのに、です。
- 世帯全体の手取り減少 ― 本人に税金や保険料がかかるだけでなく、配偶者や親の控除がなくなって税金が増えることもあります。働いたのに世帯全体では手取りが増えない、むしろ減ると感じることすらあります。
- 扶養の混同による誤解 ― 「扶養内で働きたい」という声はよく聞かれます。ただ、この「扶養」が税金上のものか社会保険上のものか、本人も分かっていない場合が多いです。結果として、収入を抑えすぎたり、逆に予想外の負担が生じたりするケースがあります。
- 社会全体への影響 ― 少子高齢化で人手不足が深刻な中、働ける人が「壁」を気にして労働時間を減らしてしまうのは、社会全体にとっても損失です。企業にとっては人材の確保が難しくなり、経済全体の活力にも影響が出てきます。
さらに近年は最低賃金が上がり続けており、同じ時間働いていても収入が増えて壁に近づく人が増えています。本人の意図に関わらず「壁」を意識せざるを得ない状況になっている、というのも最近の特徴です。
今回の制度改正の位置づけ
令和7年から始まる制度改正は、こうした「年収の壁」への対策の一つとして導入されます。
これまで、基準を意識して働き方を調整する人が多く、世帯収入の伸びを妨げる要因になっていました。企業にとっても人材確保を難しくしており、社会的な課題とされてきたのです。
今回の改正では、控除制度や税額控除の調整、社会保険の加入基準の見直しなどが行われ、基準額を引き上げたり、段差を緩やかにしたりする方向で整理が進められています。
ただし、壁そのものがなくなるわけではありません。税制や社会保険制度はそれぞれ目的を持って作られているため、一定の基準は引き続き残ります。したがって、今回の改正は「年収の壁を高くし、段差を緩やかにするための第一歩」と位置づけられるでしょう。
次回からは、この制度改正の具体的な内容を「税金編」「社会保険編」に分けて整理します。特に住民税は地域によって非課税基準が異なり、和歌山市は2級地、周辺の市町村は3級地と区分されています。この地域差にも触れながら解説していきたいと思います。
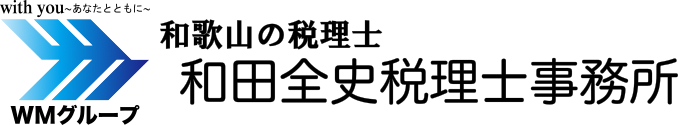
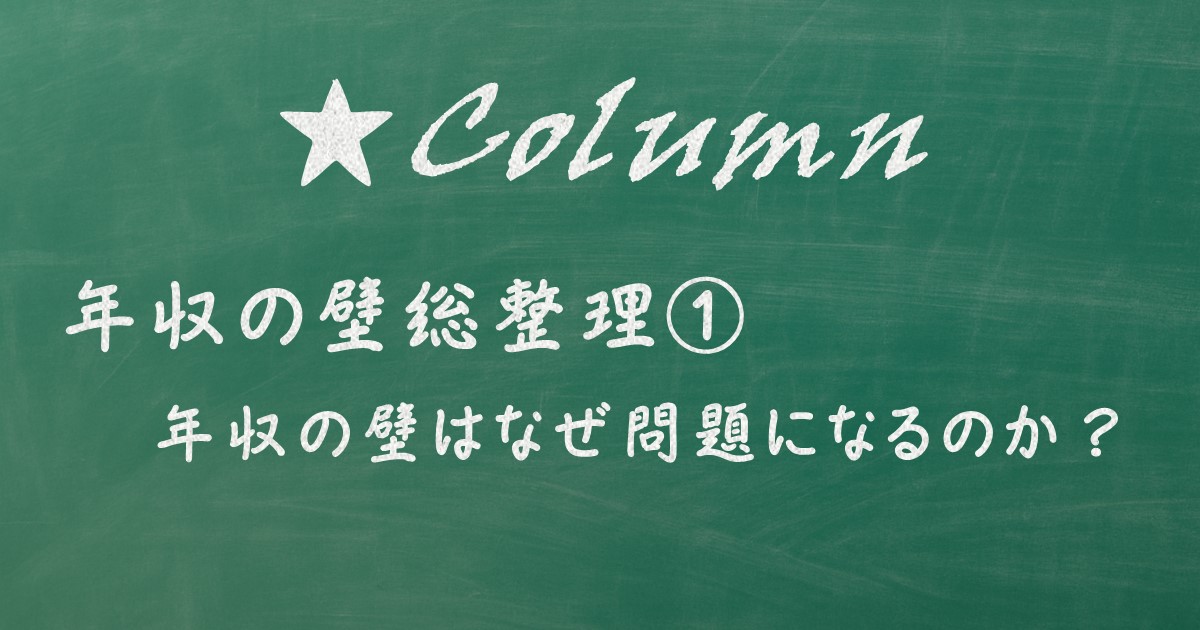
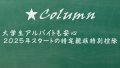
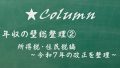
コメント