今回も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。和歌山で税理士をしております、和田全史です。
これまで「年収の壁」について税金面を中心に整理してきました。今回は社会保険の壁についてです。私は税務の専門家であり、社会保険の分野には詳しくない部分もあります。そのため、ここでは細かい実務の取り扱いまでは立ち入りませんが、仕組みの大枠を押さえていただくことを目的にしています。
社会保険の壁としてよく話題に上がるのは「106万円の壁」「130万円の壁」です。そして、令和7年(2025年)10月からは新たに「150万円の壁」が設けられる予定です。以下、この三つを中心に整理します。
社会保険の「壁」とは何か
社会保険の壁とは、収入が一定の基準を超えると、それまで扶養に入っていた人が自分で社会保険に加入しなければならなくなる、その境目のことを指します。主に配偶者や親の扶養に入っているパート・アルバイト、学生が対象になります。
-
130万円の壁:扶養に入っている人が、自分で保険料を負担する必要が出てくる基準
-
106万円の壁:大企業などで短時間労働者も社会保険に加入しなければならなくなる基準
-
新しい150万円の壁:2025年10月から導入される、19歳~22歳を対象とした特例
税金と社会保険はいずれも「壁を超えると負担が増える」という点では共通しています。ただし仕組みは異なり、税金は扶養する側の控除が減って税額が増えるのに対し、社会保険は扶養から外れることで本人に保険料の負担が生じます。
また、収入の見方にも違いがあります。税金では通勤手当のような非課税の部分は含まれませんが、社会保険ではそうした手当も収入に含めて判定されます。この違いが「思ったより早く壁を超えてしまった」ということにつながる場合があります。
130万円の壁
社会保険の壁の中で基本となるのが「130万円の壁」です。扶養に入っている人は、年間収入が130万円未満であれば扶養のままでいられますが、130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければなりません。
この基準は協会けんぽや健康保険組合が扶養認定を行う際に用いられます。判定は「今後1年間の収入見込み」で行われ、月額ではおおよそ10万8,333円が目安です。収入には基本給のほか、通勤手当・残業代・各種手当が含まれ、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けている場合も収入として扱われます。
130万円を超えると扶養から外れるため、自分で社会保険に加入しなければなりません。勤務先で加入できる場合もあれば、国民年金や国民健康保険に加入する場合もあります。いずれにしても保険料の負担が発生し、手取りは減ることになります。
106万円の壁
本来、社会保険に加入するのは「正社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上働いている人」が基本です。正社員が週40時間勤務の会社であれば、週30時間以上が目安になります。そのため、これより短い時間で働くパートやアルバイトは、原則として扶養に入り、130万円の壁が基準になります。
ただし、大企業などでは特例として、次の条件を満たすと、130万円に達していなくても社会保険に加入しなければならない場合があります。これが「106万円の壁」です。
-
週の所定労働時間が20時間以上
-
月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
-
雇用期間が2か月を超える見込み
-
学生でないこと(夜間・通信制は除く)
-
勤務先の従業員数が51人以上
この基準を超えると、パートやアルバイトでも社会保険に加入することになり、保険料が給与から天引きされます。手取りは減りますが、将来の年金額が増えたり、傷病手当金や出産手当金を受けられるといったメリットもあります。
企業規模要件について
現在は「従業員51人以上の事業所」に勤める人が対象です。つまり、同じ週20時間勤務でも小規模な事業所では加入対象外となり、130万円の壁が基準になります。
ただし、この企業規模要件は今後段階的に縮小され、最終的には撤廃される予定です。厚生労働省が示すスケジュールでは、以下のようになっています。
-
2027年10月から:従業員36人以上
-
2029年10月から:従業員21人以上
-
2032年10月から:従業員11人以上
-
2035年10月から:10人以下の事業所まで対象
今後の方向性
将来的には「106万円の壁」という金額基準がなくなり、収入にかかわらず週20時間以上働けば社会保険に加入する仕組みに変わっていく見込みです。現時点では大企業に勤める人が中心ですが、企業規模要件の縮小により、小規模な事業所で働く人にも広がっていく流れにあります。
新しい150万円の壁
先ほど書きましたように、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準は、原則として「130万円未満」です。しかし、令和7年(2025年)10月からは、この基準が一部緩和され、19歳以上23歳未満の人については「150万円未満」とされます。
対象は主に大学生や専門学校生で、親の扶養に入っているケースです。これまでならアルバイト収入が130万円を超えると扶養から外れ、保険料を自分で負担する必要がありましたが、制度改正後は150万円までであれば扶養にとどまることができます。
同時期に税制面でも「特定親族特別控除」が導入され、19歳~22歳を対象に控除額が拡大されます。制度は別ですが、どちらも若い世代が学業と就労を両立しやすくするための流れの一環といえます。
社会保険の壁と働き方の選択
主婦パートの場合
まず意識されるのは社会保険の「130万円の壁」です。130万円を超えると扶養から外れて保険料の負担が発生するため、「扶養内で働くか」「思い切って超えて社会保険に加入するか」という選択が必要になります。
税制面では、かつては「103万円」が大きな目安とされていました。平成30年(2018年)の改正で配偶者特別控除が拡充され、150万円までは満額、約201万円までは段階的に控除が残る仕組みとなりました。令和7年(2025年)の改正では、配偶者控除の基準が103万円から123万円に引き上げられ、配偶者特別控除を満額受けられる基準も160万円に引き上げられましたが、基本的な構造は変わっていません。したがって、税金だけを見れば急激に負担が増えるわけではなく、実際には社会保険の130万円の方が大きな影響を持つケースが多いといえます。
なお、勤務先が大企業の場合は、106万円の壁が先にかかることもありますが、「扶養内で働くか」「思い切って超えて社会保険に加入するか」という選択が必要になる点は同じです。
大学生アルバイトの場合
これまでは税制面の「103万円の壁」が大きな目安でした。103万円を超えると本人に税金がかかるだけでなく、親の扶養控除も使えなくなり、世帯全体で税負担が増えるため、多くの学生は103万円を超えないように調整していました。さらに収入が増えると、社会保険の「130万円の壁」にも影響し、扶養から外れて保険料を自分で負担しなければなりませんでした。
今回の改正で、19歳~22歳の人は社会保険の基準が150万円未満まで緩和されます。税制と社会保険の両面で調整が進むことで、これまでより働きやすくなることが期待されます。
まとめ
社会保険の壁には、基本となる「130万円の壁」、大企業などで適用される「106万円の壁」、そして2025年10月から導入される「新しい150万円の壁」があります。税金の壁と同じく、いずれも「壁を超えると負担が増える」という点では共通しています。ただし仕組みは異なり、税金は扶養する側の控除が減って税額が増えるのに対し、社会保険は扶養から外れることで本人に保険料の負担が生じます。収入の見方にも違いがあり、通勤手当など税金では非課税の部分も、社会保険では収入に含めて判定されます。
今後は、106万円の壁の撤廃や、19歳~22歳を対象とした150万円の壁の導入など、社会保険制度の見直しが進んでいきます。こうした動きを踏まえれば、従来より働き方の選択肢が広がっていくことが期待されます。
なお、具体的な適用や判断は加入先や勤務先によって異なるため、実際に確認が必要です。
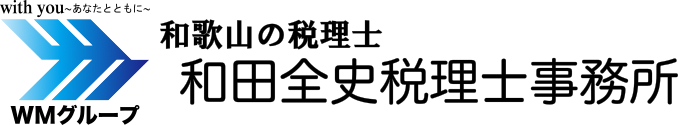
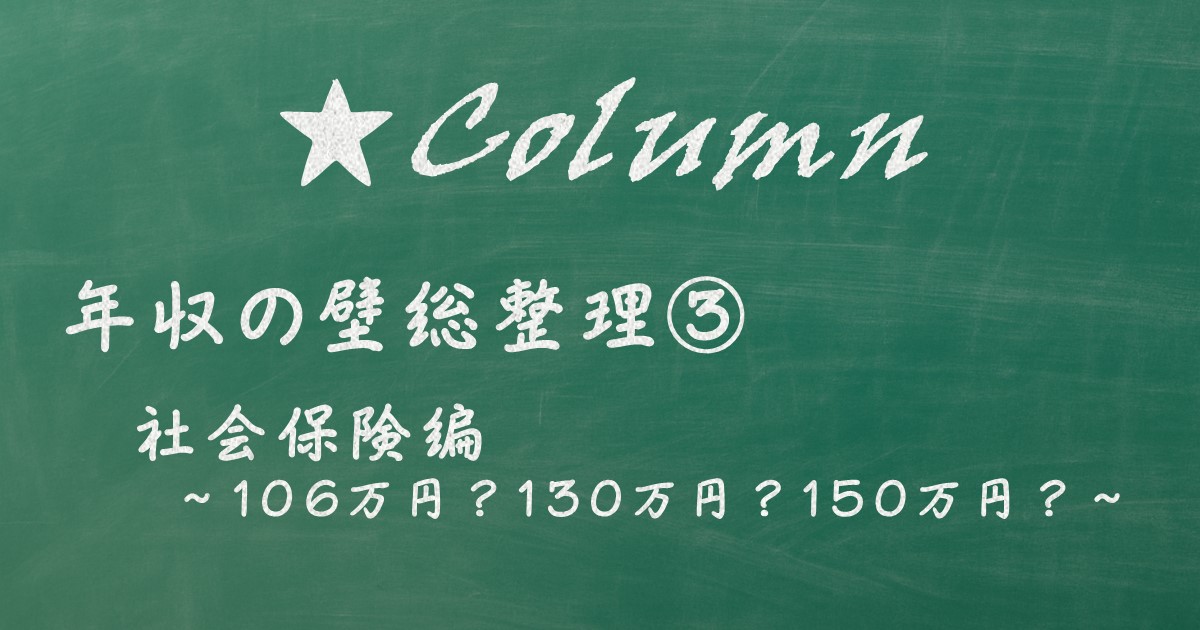
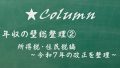
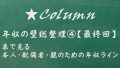
コメント