和田全史税理士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
先日の参議院選挙を受けて、「今後の税制はどうなるのか?」に関心が高まっています。その中でも話題に上がっているのが、消費税の減税です。
現時点ではまだ決まっていませんが、もし実際に減税が実施されることになれば、事業者にとってもさまざまな影響があります。今回は、主に中小事業者の視点から、消費税減税の可能性とその影響について整理してみます。
消費税は「預り金」のようで、実はそうではない
「消費税はお客さまから預かったお金を納めるだけ」と思われがちですが、実は正確にはそうではありません。消費税は、いわゆる「付加価値税」の性格を持つものです。
つまり、売上にかかる消費税(仮受消費税)から、仕入や経費にかかった消費税(仮払消費税)を差し引いて、差額を納める仕組みになっています。これが本来の計算方法であり、「本則課税(原則課税、一般課税とも)」と呼ばれます。
課税方式の違い:本則課税と簡易課税
中小企業などでは、「簡易課税制度」を選んでいるケースもあります。簡易課税では、実際の仕入や経費にかかわらず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づいて納税額を計算します。
この仕組みにより、簡易課税では本則課税に比べて納税額が少なくなるケースが多く、いわゆる「益税」が発生しやすくなります。したがって、消費税率が下がると受け取る消費税も減り、結果として益税も減る可能性があります。
簡易課税を選んでいる事業者にとっては、「減税=必ず得する」とは限らない点に注意が必要です。
食品の消費税率が0%(免税)になったら?(スーパーなどの場合)
「食料品の消費税を0%に」といった案も報じられています。仮にそのような措置が取られ、食品が免税扱いになった場合、スーパーなどの小売業者には次のような影響が考えられます。
- 食品の売上およびその仕入は免税となり、消費税が発生しない。
- 一方、光熱費や通信費、事務用品などの共通経費には引き続き消費税がかかる。
- 現行制度であれば、免税売上があっても共通経費にかかる消費税は全額仕入税額控除が可能。
ただし、現時点で制度の詳細は決まっておらず、今後の制度設計によっては控除割合の制限や計算方法の変更があるかもしれません。実務への影響は小さくない可能性があります。
実務的な対応や負担も増えるかも?
消費税率の変更は、数字の調整だけではありません。実務面でも次のような対応が求められます:
- レジや会計ソフトの設定変更
- 請求書・見積書の書式の見直し
- 商品の値札の付け替え・価格表示の変更
- 社内ルールの変更、取引先への説明など
特に現在はインボイス制度も施行されており、請求書や帳簿の管理が厳格化されています。税率変更と重なれば、現場の負担はより大きくなるでしょう。
まとめ:減税は「必ずしも得」とは限らない
消費税の減税は、消費者にとって歓迎される政策ですが、事業者にとっては必ずしも「得」になるとは限りません。
- システム・帳簿の調整やコスト
- 制度変更に伴う経理・申告の複雑化
- 簡易課税のいわゆる益税が減る可能性
税率が下がるとしても、その内容次第で影響は大きく変わります。今のうちから「自社にはどんな影響があるか?」を想定しておくことが大切です。
当事務所では、消費税の制度変更や課税方式の見直し、影響試算などのご相談にも対応しております。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
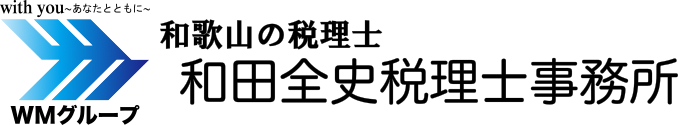



コメント