和歌山の和田全史税理士事務所です。いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
老後資金の準備に関しては、2024年末の税制改正大綱や、2025年6月13日に成立した年金制度改正法などでも大きく取り上げられています。その中でも「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、節税効果と資産形成を同時に実現できる制度として注目を集めています。
今回からは、このiDeCoについてシリーズで解説していきます。まずは制度の基本と掛金拠出による節税メリット、そして2027年から予定されている改正ポイントを整理します。
iDeCoとは?制度の基本
iDeCoの概要
iDeCoは、公的年金に上乗せして利用できる「自分年金づくり」の制度です。少子高齢化が進むなかで、公的年金だけでは将来の生活費をまかなうのが難しくなるのではないかと心配する声も増えています。その不足分を自分自身で準備する手段として、iDeCoは注目されています。
加入者自身が毎月掛金を拠出し、その掛金を投資信託や定期預金などで運用し、老後に年金または一時金として受け取ります。
大きな特徴は、税制優遇が三段階で受けられる点です。掛金は全額所得控除、運用益は非課税、受け取り時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。そのため、老後資金の準備と節税を同時に進められる仕組みとなっています。
加入できる人と掛金上限(現行)
iDeCoは国民年金の被保険者区分ごとに掛金の上限額が決められています。基本的には次のように整理できます。
| 区分 | 主な対象者 | 月額掛金上限 | |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、フリーランスなど | 68,000円 | |
| 第2号被保険者 | 企業年金なし | 勤務先に企業年金制度のない会社員・役員 | 23,000円 |
| 企業年金あり | 確定給付企業年金など、他の企業年金制度に加入している会社員・役員 | 20,000円 | |
| 公務員 | 国家公務員・地方公務員(共済組合に加入) | 20,000円 | |
| 第3号被保険者 | 専業主婦(夫)など | 23,000円 | |
注意点
- 第1号被保険者の月額6.8万円は、iDeCo単独の上限ではなく、国民年金基金や付加保険料との合算枠です。
- 第2号被保険者で「企業年金あり」の場合は、勤務先の企業年金掛金と合わせて全体で月5.5万円以内に収まるよう調整されます。そのため、会社拠出が大きい人ほどiDeCoで拠出できる額は少なくなります。
- 大枠としては「自営業は枠が広い」「会社員や公務員は勤務先の制度によって変わる」「専業主婦(夫)も23,000円まで可能」と理解しておけば十分です。実際の拠出可能額は、加入時に金融機関や勤務先から案内されます。
掛金拠出による節税メリット
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除されます。拠出した金額がそのまま課税所得から差し引かれるため、税率に応じて大きな節税効果が得られます。
- 個人事業主の場合
最大で月68,000円(年間816,000円)を拠出可能。所得税・住民税の合計税率が30%の人なら、年間約24万5,000円の節税効果となります。小規模企業共済(年間84万円まで拠出可能)と並び、自営業者にとって代表的な節税手段です。 - 会社員・法人役員の場合
例えば月23,000円(年間276,000円)を拠出すると、税率30%で年間約8万3,000円の節税効果です。勤務先に企業年金制度がある場合は上限が2万円となりますが、それでも年間7万2,000円程度の節税になります。
さらに、運用益は非課税で、通常なら約20%かかる譲渡益課税もかかりません。つまり、掛金時・運用時の両面で税制メリットがある制度といえます。
注意点
- 小規模企業共済等掛金控除は加入者本人分のみが対象です。社会保険料控除のように家族分を負担して控除することはできません。
- そのため、第3号被保険者(専業主婦(夫)等)は所得が少なく、掛金時の節税メリットを受けにくい点に注意が必要です。
2027年からの制度改正ポイント
iDeCoに関しては、昨年末に公表された税制改正大綱で方向性が示されていました。その内容を受けて、2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、2027年からの制度拡充が予定されています。
今回の改正では、掛金の上限額や加入可能年齢が大きく見直され、より多くの人が利用しやすい制度に変わっていきます。
- 第1号被保険者(自営業等)
月6.8万円 → 7.5万円。引き上げ幅は小さいですが、引き続き大きな節税手段です。 - 第2号被保険者(企業年金なし)
月2.3万円 → 6.2万円。会社員や役員で勤務先に年金制度がない人は、大幅に拠出余地が広がります。 - 第2号被保険者(企業年金あり・公務員含む)
月2.0万円 → 最大6.2万円。勤務先の企業年金掛金と合算で枠が決まるため、実際の拠出可能額は人によって異なります。 - 第3号被保険者(専業主婦(夫)等)
現行のまま月2.3万円。据置(変更なし)。 - 加入可能年齢の拡大
現行は65歳未満 → 70歳未満へ拡大予定。より長い期間、節税と資産形成が可能になります。
まとめ
iDeCoは、掛金が全額所得控除となるため、まず「掛けるときの節税効果」が大きな魅力です。加えて、運用益が非課税、受け取るときも退職所得控除や公的年金等控除が使えるなど、税制上の優遇が手厚く用意されています。
2025年6月に成立した年金制度改正法を踏まえ、2027年からは制度が拡充され、特に会社員や公務員にとって掛けられる額が大幅に増える予定です。自営業の方には引き上げ幅は小さいですが、もともと上限が大きいため、引き続き有力な選択肢です。
制度の細かい条件は人によって異なるので、最終的には勤務先や運営管理機関に確認する必要があります。ただ、まずは「誰でも利用できて、節税しながら老後資金をつくれる制度」だと理解しておけば十分です。
次回は、iDeCoと国民年金基金・小規模企業共済などとの比較を解説します。
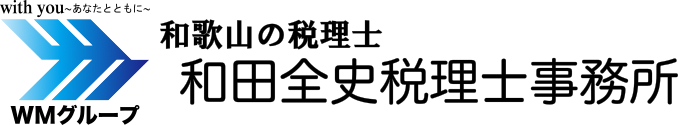

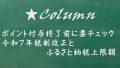

コメント