和歌山の和田全史税理士事務所です。いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、iDeCoに加えて「国民年金基金」「小規模企業共済」を取り上げ、三つの制度の違いをシンプルに整理します。誰でも自由に選べるわけではなく、立場(自営業・会社役員・会社員)によって使える制度や優先順位が変わる点に注意しながら進めます。
制度の目的と性格
iDeCo(個人型確定拠出年金)
自分で掛金を拠出し、運用先も自分で選ぶ私的年金。掛金は全額所得控除。資産形成型で、増える可能性もある一方、元本割れリスクもあります。資金は原則60歳まで引き出し不可です。
国民年金基金
第1号被保険者(自営業・フリーランス)専用の「公的年金の上乗せ」。掛金は全額所得控除。基本は終身年金で長生きリスクに備える設計。受給開始は原則65歳(タイプにより60歳)。途中解約不可で資金拘束は強いです。
小規模企業共済
個人事業主・小規模法人の役員の退職金づくりの制度。掛金は全額所得控除。事業廃止・役員退任・65歳以上の老齢給付・死亡などで共済金を受給。任意解約は可能(短期は元本割れリスク)で、三制度の中では比較的柔軟です。
加入資格の違い
iDeCo
国民年金の被保険者であれば加入可(第1号・第2号・第3号)。※区分により掛金上限が異なる。
国民年金基金
第1号被保険者限定(会社員・第3号は不可)。
小規模企業共済
個人事業主・共同経営者・小規模法人の役員(会社員・第3号は不可)。
掛金と拠出ルールの違い
iDeCo
第1号:月6.8万円まで(国民年金基金と合算枠)
第2号:月2.0〜2.3万円(勤務先の企業年金の有無で変動)
第3号:月2.3万円
※第1号は基金と同じ枠を取り合うため、基金 or iDeCoの選択が必要。
国民年金基金
iDeCoと合算で月6.8万円が上限。
※基金で枠を使うとiDeCoに回せません。
小規模企業共済
月1,000円〜7万円(500円単位)で柔軟に設定。
別枠のため、iDeCo・基金と併用可。
受給と税制の仕組み
iDeCo
拠出:掛金は全額所得控除
運用:運用益は非課税
受給:一時金=退職所得控除/年金=公的年金等控除
国民年金基金
拠出:掛金は全額所得控除
運用:基金内で運用(課税は受給時)
受給:年金のみ(公的年金等控除の対象)
小規模企業共済
拠出:掛金は全額所得控除
運用:共済内で運用(課税は受給時)
受給:
・共済金(廃業・退任・老齢給付など)= 一時金:退職所得控除/年金:公的年金等控除
・解約手当金(任意解約)= 一時所得
立場別の使い分け
自営業者・フリーランス:小規模企業共済 + 国民年金基金 or iDeCo
(共済で退職金、基金/iDeCoで上乗せ。安定志向=基金、投資志向=iDeCo)
会社役員(小規模法人):小規模企業共済 + iDeCo
(共済で退職金を確保、iDeCoで年金資産形成)
会社員・公務員:iDeCo
(共済・基金は不可。勤務先の企業年金の有無で上限が変動)
制度の違いを比較表で整理
| 項目 | iDeCo | 国民年金基金 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|---|
| 加入資格 | 国民年金の被保険者(第1号〜第3号) | 第1号被保険者のみ | 個人事業主・小規模法人の役員 |
| 掛金上限 | 第1号:月6.8万円(基金と合算) 第2号:月2〜2.3万円 第3号:月2.3万円 |
iDeCoと合算で月6.8万円 | 月1,000円〜7万円(500円単位) |
| 所得控除 | 掛金全額が所得控除 | 掛金全額が所得控除 | 掛金全額が所得控除 |
| 受給 | 一時金=退職所得控除 年金=公的年金等控除 |
年金のみ=公的年金等控除 | 共済金:一時金=退職所得控除/年金=公的年金等控除 解約手当金=一時所得 |
| 備考 | 原則60歳まで引き出し不可/運用益も非課税 | 原則65歳開始(タイプにより60歳)/途中解約不可 | 任意解約可(短期解約は元本割れリスク) |
まとめ
三つの制度はいずれも掛金が全額所得控除となり、老後資金や退職金準備に有効です。ただし、加入できる人・掛金枠・受給方法・柔軟性は異なります。
自営業者は「小規模企業共済」をベースに、安定志向なら国民年金基金、投資志向ならiDeCo。会社役員は「小規模企業共済+iDeCo」。会社員・公務員は「iDeCo」が中心です。
「どれが一番良いか」ではなく、立場や目的に合わせて組み合わせるのが最適解です。次回は、iDeCoの出口戦略(受け取り方と税制メリット)を解説し、実際の取り崩しと税効率の考え方を整理します。
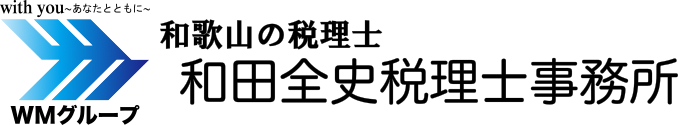
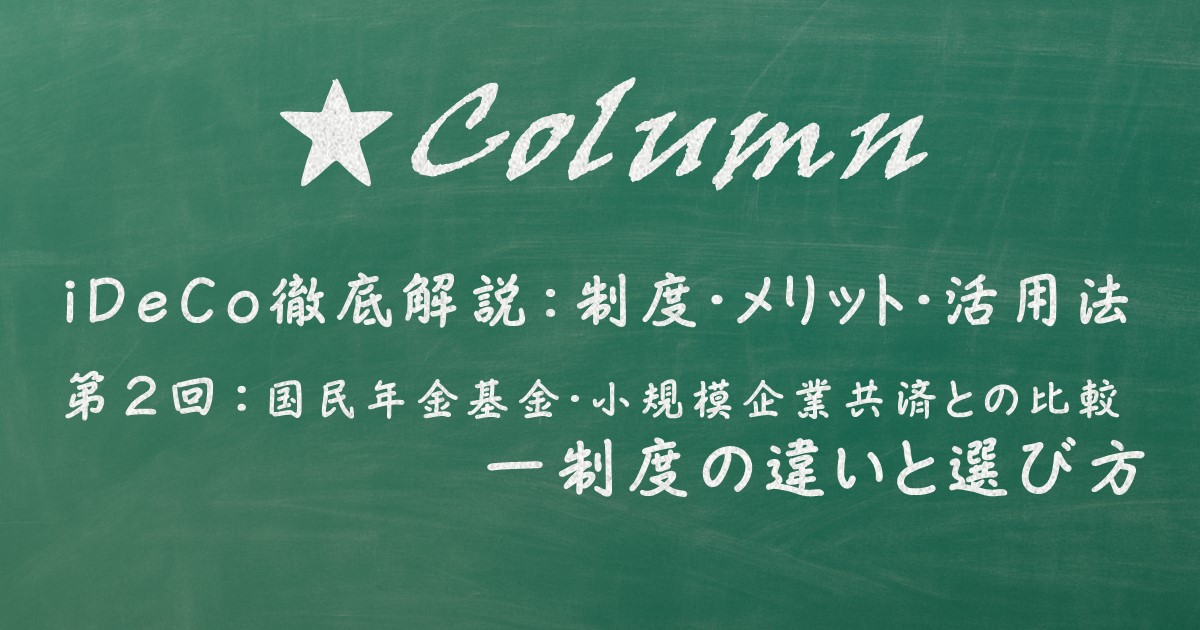


コメント