和歌山の和田全史税理士事務所です。ブログをご覧いただきありがとうございます。
最近のニュースを見ていると、「給付付き税額控除」という制度の名前をよく見かけるようになりました。2025年7月の参議院選挙後、物価高や消費税の負担をどう軽くするかが再び大きなテーマになり、その中でこの制度も検討対象に上がっています。
野党の立憲民主党が「消費税の逆進性」を和らげる対策として提案し、8月には自民党との間でも政策協議のテーブルに乗りました。まだ導入が決まったわけではありませんが、少し前より現実味のある話になってきたように感じます。
給付付き税額控除って何?
名前だけ聞くと難しそうですが、仕組みはシンプルです。税額控除というのは、住宅ローン控除などであるように、計算した税額から直接差し引くものです。
例えば、払うべき税金が5万円で、税額控除が10万円あったとします。今の制度では、5万円は引けても残りの5万円は使えずに消えてしまいます。
給付付き税額控除は、この使い切れなかった分を現金で支給する制度です。納税額が少ない人や、そもそも納税していない人でも、条件に合えばお金がもらえるという仕組みです。
なぜ「税額控除」でやるのか?
「所得控除じゃだめなの?」と思うかもしれません。所得控除は課税前の所得から差し引くので、税率が高い人ほど効果が大きく、税率が低い人ほど効果が小さくなります。つまり、所得が少ない人には恩恵が届きにくいのです。
税額控除なら、税率に関係なく同じ金額を直接税額から引けます。さらに給付付きにすれば、そもそも税金を払っていない人にも支援を届けられます。公平性という面で、税額控除の形を取る理由はここにあります。
単なる給付とどう違う?
過去の定額給付金は、所得に関係なく全員に配られました。スピード感はありますが、収入の多い人も少ない人も同じ額というのは、再分配の効果としては弱めです。
給付付き税額控除は、税制度の中で所得や条件を確認しながら支給します。必要な人に絞り込めて、毎年同じルールで続けられるのが大きな違いです。
なぜ今、注目されているのか?
一番の背景は、物価の上昇と消費税の逆進性です。収入が少ない人ほど、生活必需品への支出割合が高く、そこに一律で消費税がかかると負担感が大きくなります。
これまでにも定額給付金などで一時的な支援はありましたが、その都度制度を作るのは手間もコストもかかります。給付付き税額控除なら、年末調整や確定申告とセットで自動的に支給できるので、必要な人に届きやすいというメリットがあります。
実務への影響は?
もし導入されたら、年末調整や確定申告の様式変更、給与計算ソフトの対応など、事務作業の見直しが必要になる可能性があります。従業員を雇っている事業者であれば、年末調整の計算や控除の適用方法に新しい項目が加わるかもしれません。
また、制度の詳細次第では、対象者の判定や説明のための準備も必要になります。マイナンバー制度の整備が進んでいるため、所得の把握や支給対象の確認は以前より行いやすくなっています。
まとめ
給付付き税額控除は、低所得層への支援と税制の公平性を両立できる仕組みとされます。税額控除として行うことで税率による不公平を避けられ、給付付きにすることで納税していない人にも支援が届くと考えられています。
参院選後の政策議論の中でも再び名前が出てきており、今後の税制改正の中で重要なテーマになる可能性があります。制度の詳細が固まる前に、自社やご自身にどんな影響があるかを一度シミュレーションしておくと安心です。
当事務所では、制度変更への対応や影響試算のご相談にも対応しております。気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください。
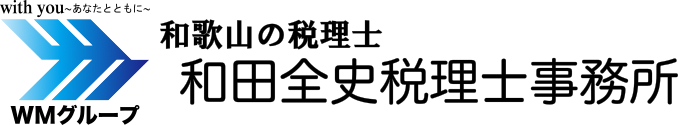



コメント