こんにちは。和歌山で税理士をしております、和田全史です。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
これまでのシリーズでは、まず「所得税・住民税の壁」を整理し、その後「社会保険の壁」について見てきました。最終回となる今回は、それらを横断的にまとめ、全体像をひと目で確認できるように整理します。
なお、本記事では理解しやすいように「給与収入」を基準に説明していますが、実際の税制上の判定は「合計所得金額」によって行われます。
「本人の年収」が一定のラインを超えると、自分自身だけでなく、配偶者や親の税制・社会保険にも影響が及びます。そうした関係性を一覧にしたのが次の表です。まずは全体像を見渡してみましょう。
「年収の壁」を表で整理する
| 給与収入 | 本人 | 配偶者 | (主に) 親 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民税 | 所得税 | 社会保険 | 配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
扶養控除 | 特定親族 特別控除 |
|||
| 51人未満 | 51人以上 | 19~22歳 | |||||||
| ~103万円 | 3級地 非課税 |
課税 されない |
扶養OK | 扶養OK | 扶養OK | 適用 | – | 適用 | – |
| ~106万円 | 2級地 非課税 |
||||||||
| ~106.5万円 | 加入義務の可能性 (週20h・月額8.8万円等) |
||||||||
| ~110万円 | 1級地 非課税 |
||||||||
| ~123万円 | – | ||||||||
| ~130万円 | – | 満額 | – | 逓減 | |||||
| ~150万円 | – | – | |||||||
| ~160万円 | – | ||||||||
| ~188万円 | – | 逓減 | |||||||
| ~201.6万円 | – | ||||||||
表のポイント解説
今回の表は、本人の年収を基準に、税金や社会保険、さらには配偶者控除や親の扶養控除への影響を横断的に整理したものです。
- 税金の壁
住民税は地域区分によって非課税ラインが異なり、3級地は103万円、2級地は106.5万円、1級地は110万円です。和歌山市は2級地、周辺の市町村は3級地となっており、同じ収入でも住民税の負担開始が異なる点に注意が必要です。
所得税は160万円を超えると課税が始まります。(基礎控除以外の所得控除がない場合) - 社会保険の壁
原則は「130万円の壁」で、超えると本人が社会保険に加入する可能性があります。
大企業などでは「106万円の壁」があり、所定要件(週20時間・月額賃金8.8万円など)を満たすと加入義務となります。
令和7年10月からは、19~22歳(大学生アルバイトなど)を対象に「150万円の壁」が導入されます。 - 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除は本人年収123万円まで適用されます。
123万円を超えると配偶者特別控除となり、160万円までは満額、その後201.6万円未満までは段階的に減少します。 - 親の扶養控除・特定親族特別控除
扶養控除は本人年収123万円までが対象です。
19歳から22歳までは「特定親族特別控除」があり、123〜188万円の範囲で段階的に減少します。
典型的なパターン
主婦パートの場合
本人の年収が123万円までは、配偶者に配偶者控除が適用されます。これを超えると配偶者特別控除に切り替わりますが、160万円までは満額の控除が続きます。したがって、160万円までは配偶者の税負担に大きな変化はありません(※老人控除対象配偶者の場合は異なります)。
一方で、社会保険については130万円を超えると扶養から外れ、本人が加入しなければならなくなります。大企業などに勤務している場合には、その基準が106万円になることもあります。
令和7年からの改正により税制面では負担が軽減される方向にありますが、社会保険の壁は依然として大きく、結果として令和6年以前と比べても実感としては大きな変化がないといえるでしょう。
19~22歳(大学生アルバイトなど)の場合
本人の年収が123万円までは、親に扶養控除が適用されます。123万円を超えると特定親族特別控除に移行し、188万円までの間は段階的に減少していきます。本人の年収が増えるに従って、親の税負担が増えることになります。
また、社会保険に目を向けると、原則として130万円を超えると扶養から外れ、本人が社会保険に加入する必要がありますが、令和7年10月からは19~22歳を対象に「150万円の壁」が新たに導入されます。これを超えると学生であっても社会保険に加入する可能性があり、現実的にはこの負担を避けるために150万円までに収入を抑えるケースが多くなると考えられます。
まとめ
今回まで4回にわたり「年収の壁」を整理してきました。所得税・住民税、社会保険、配偶者控除や扶養控除といった仕組みはそれぞれ異なる基準を持っており、単独で見ると複雑に感じられます。
しかし、表で横断的に整理すると、「本人の年収がどのラインを超えると、本人・配偶者・親の税制や社会保険に影響が及ぶのか」が一目で把握できます。
ポイントは、
- 税金は令和7年の改正で緩和傾向にある一方、社会保険は依然として大きな負担要素として残っていること
- 配偶者や親の控除は、本人の年収によって段階的に減少・消滅すること
- 特に主婦パートの「130万円(規模により106万円)」、大学生アルバイトの「150万円」のラインは社会保険料の負担が急に発生し、手取りに大きな影響を与える可能性があること
最終的には、世帯全体での税・社会保険のバランスを踏まえながら、働き方や収入調整を考えることが重要になります。今回の記事が、その判断の一助になれば幸いです。
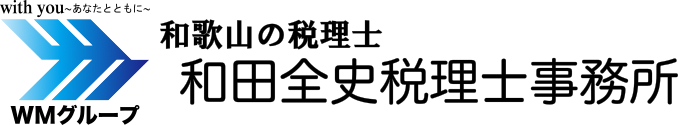
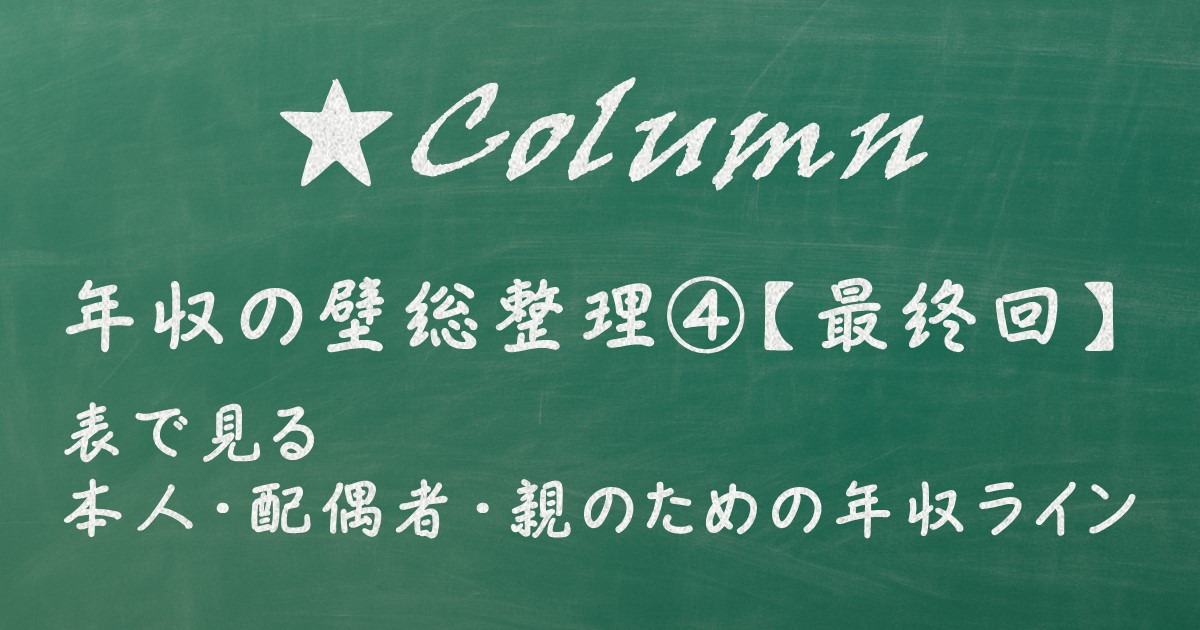

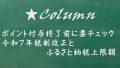
コメント