和歌山の和田全史税理士事務所です。いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
これまで3回にわたり、iDeCoの制度や拠出メリット、他制度との比較、そして受け取り方と税制メリットについて解説してきました。今回がシリーズの最終回です。
テーマは「リスク管理とリバランス戦略」。iDeCoは長期にわたり積み立てる制度であり、かつ加入者自身が商品を選んで運用する仕組みになっています。そのため、積み立てるだけでなく、時には資産配分を見直すことも大切です。本記事では、長期投資の基本的な考え方を整理し、iDeCo特有の制約を踏まえた工夫について紹介します。
資産配分(アセットアロケーション)の考え方
資産配分(アセットアロケーション)とは、株式・債券・定期預金などをどのくらいの割合で保有するかを決めることです。投資の成果は個々の商品選びよりも、この配分のほうが大きく影響すると言われています。
- 株式:値動きが大きい一方で、長期的には高いリターンを期待できる資産
- 債券や定期預金:値動きが小さく、安全性を重視できる資産
- 不動産投資信託(REIT)や金(ゴールド)関連投信:株式や債券と異なる値動きをすることが多く、分散効果を高める資産
このように複数の資産を組み合わせることで、運用全体のバランスを取りやすくなります。株式を多めにすればリターンの可能性は高まりますが、価格変動も大きくなります。逆に安全資産を多めにすれば安定性は高まりますが、将来の増え方は控えめになります。
ひとつの目安として、「株式:債券=6:4」や「5:5」といった極端に偏らない配分がよく用いられます。さらに、国内と海外を組み合わせることで、特定の市場の影響を受けにくくする効果もあります。
大切なのは「正解が一つあるわけではない」という点です。自分の目的やリスク許容度に応じて、無理のない比率を決めることが第一歩となります。なお、iDeCoは毎月一定額を積み立てる仕組みのため、自然にドルコスト平均法(定額購入法)の効果が働きます。価格が高いときには少なく、安いときには多くの口数を買うことになり、結果として長期的に購入単価を平準化できる点も特徴です。
年齢やライフステージに応じたリスク調整
資産配分は一度決めたら終わりではなく、受給開始までの残り年数を意識して見直していくことが大切です。iDeCoは途中で引き出せず、受給開始時期もおおむね決まっているため、受け取りが近づくにつれて安全資産を増やすのが一般的です。
ここでいう「安全資産」とは、値動きが比較的小さい資産、すなわち債券(国内債券・先進国債券)を中心に指します。定期預金や保険商品も安全資産に含まれますが、利率が低いため、実際には債券型投資信託を選ぶ人が多いのが実情です。
- 若い時期(20代~30代):受給まで時間が長いため、一時的な値下がりがあっても回復の余地があります。株式比率を高めに(例:株式70%、安全資産30%)するケースが一般的です。
- 中堅期(40代~50代):受給開始までの期間が短くなり、将来の受け取りを意識するようになります。株式と安全資産を半分ずつ、あるいはやや安全資産を増やす(例:株式50%、安全資産50%)配分がよく見られます。
- 退職が近づく時期(60代前後):受給が目前に迫るため、大きな値下がりを避けることが最優先です。安全資産を中心に(例:株式30%、安全資産70%)、資産の変動を抑える配分が基本となります。
また、iDeCoの商品にはREITや金を対象にした投資信託が含まれる場合もあります。これらは株式や債券と異なる値動きをするため、分散効果を高める補完的な資産として活用できます。
リバランス(資産の比率調整)の重要性
資産配分は一度決めても、時間の経過とともに崩れていきます。株式市場が好調な時期には株価が上昇し、数量は変わらなくても評価額が増えるため、株式の比率が高まります。逆に株価が下落すれば比率は下がり、リスクを取らなさすぎる状態になることもあります。
こうした偏りを元に戻す作業が「リバランス」です。例えば、
- 株式が増えすぎた場合 → 一部を売却して債券に回す
- 株式が減りすぎた場合 → 債券の一部を売却して株式を買い足す
このようにリバランスを行うことで、当初想定していたリスク水準を維持できます。
リバランスの方法は大きく分けて2つあります。
- 定期的に見直す方法(例:年1回や半年に1回)
- 一定のズレが生じたときに行う方法(例:株式比率が±5%以上動いたら調整)
どちらが正しいというわけではありませんが、「決まったルールで淡々と行う」ことが大切です。感情に左右されず、長期的な運用を続ける仕組みとして機能します。
もっとも、リバランスをするには現状把握が前提です。ほったらかしでは資産配分の変化に気づけません。iDeCoでは運営管理機関から定期的に報告書が届きますし、多くの金融機関ではWebで確認できます。これらを活用してチェックする習慣を持つことが安心につながります。
iDeCoならではの制約と工夫
iDeCoには制度特有の制約があります。
- 商品ラインナップが限られている:最大でも35本程度。金融機関ごとに内容は異なり、必ずしも理想的な商品が揃うわけではありません。
- 売買のタイミングに制約がある:発注から約定まで数日かかるのが一般的。短期売買は難しく、長期前提で考える必要があります。
- 手数料がかかる:共通部分に加え、運営管理機関ごとに差があります。商品とあわせて金融機関選びが重要です。
工夫できる点としては次のとおりです。
- 金融機関選びを工夫する:低コストのインデックスファンドを中心に扱う金融機関を選ぶことが長期的に有利です。
- 掛金の配分変更を活用する:既存資産を売却せず、毎月の掛金の行き先を調整して資産バランスを整える方法です。
- シンプルな商品構成にする:株式インデックス1本+債券インデックス1本程度でも十分な分散効果があります。
- インデックスとアクティブの違いを理解する:インデックスは指数連動で低コスト、アクティブは独自運用で成果を狙うが手数料が高め。iDeCoではインデックスを選ぶ人が多いですが、納得できるアクティブを一部取り入れる考え方もあります。
- 全体の資産で役割分担を考える:生活資金や教育資金は流動性の高い預金などで確保し、iDeCoは老後資金と割り切る。このように全体を見渡して役割を分けるのも一つの考え方です。
まとめ
今回のテーマは「リスク管理とリバランス戦略」でした。iDeCoは長期積立制度であり、資産配分の設計や定期的なリバランスが欠かせません。株価変動で比率は自然に崩れるため、定期的な確認と調整が重要です。さらに、商品数や売買制限、手数料といった制約を踏まえ、掛金配分の見直しや金融機関選びなどで工夫することが現実的です。
ここまでのシリーズでは、第1回で制度概要と拠出メリットを整理し、第2回で他制度との比較を行い、第3回で受け取り方と税制優遇を解説しました。そして今回の第4回では、運用の工夫としてリスク管理とリバランスを取り上げました。
私自身もiDeCoを利用していますが、老後資金づくりを考えるうえで有効な仕組みだと感じています。本シリーズを通じて、iDeCoの制度内容から拠出、受け取り、運用までを見通すきっかけにしていただければ幸いです。
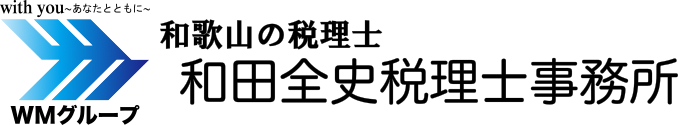
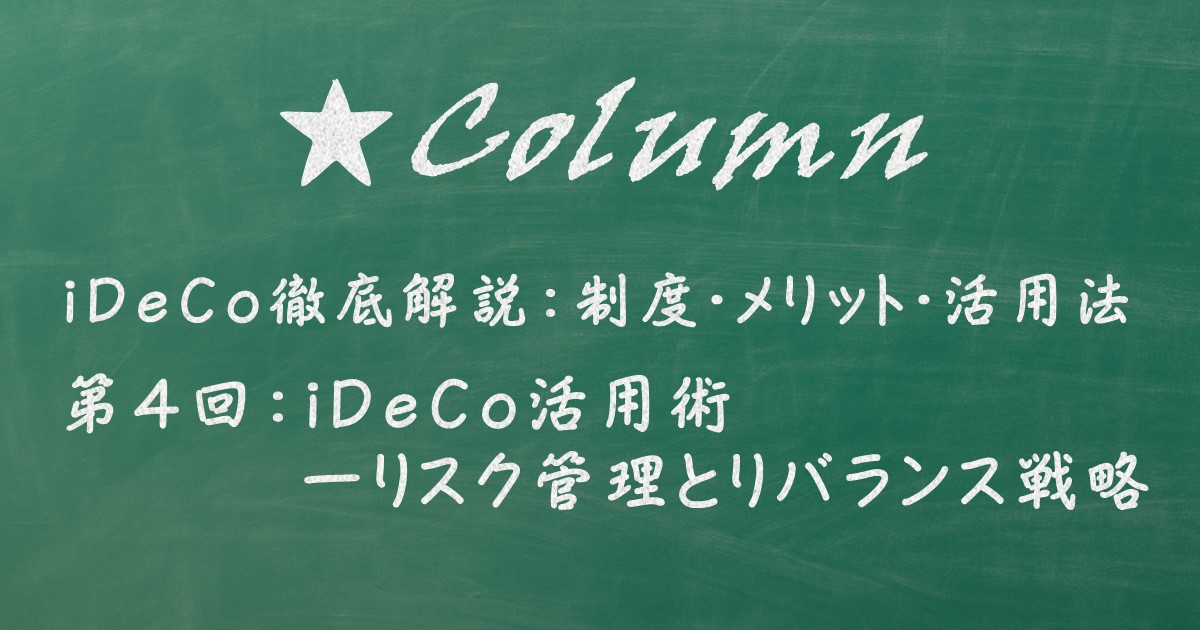


コメント