本記事では、こうした議論を前提に、仮に飲食料品が免税(ゼロ税率)とされた場合、卸売・小売・製造業および飲食店の実務や経営判断にどのような影響が生じ得るのかを整理しています。
※以下は、以前公開した記事を、直近の議論状況を踏まえて加筆・修正したものです。
和歌山の和田全史税理士事務所です。
前回の記事では、「飲食料品は消費税の対象としない」という連立政権合意書の方針について、その内容と背景を整理しました。今回は、もしこの方針が実際に法制化された場合、どのような業種に影響が及ぶのかを見ていきたいと思います。
特に、飲食料品の売上や仕入の割合が大きい飲食料品卸売・小売・製造業、そして飲食店は、制度変更の影響を最も強く受けることが予想されます。一方で、その他の業種(例えば建設業や製造業のうち飲食料品を扱わない分野など)は、経費の一部に飲食料品が含まれる程度で、影響は限定的でしょう。
この記事では、これらの業種に焦点を当てながら、免税(ゼロ税率)方式が導入された場合の実務上の影響を整理していきます。
消費税のしくみをおさらい
消費税は「お客さまから預かったお金を納めるだけ」と思われがちですが、実は正確にはそうではありません。消費税は、いわゆる付加価値税の性格を持つものです。
つまり、売上にかかる消費税(仮受消費税)から、仕入や経費にかかった消費税(仮払消費税)を差し引いて、差額を納める仕組みになっています。これが本来の計算方法であり、本則課税(原則課税、一般課税とも)と呼ばれます。
一方、前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者などは、実額ではなく業種ごとの「みなし仕入率」で計算する簡易課税制度を選択できます。
主な業種とみなし仕入率は次のとおりです。
- 第1種(卸売業):90%
- 第2種(小売業):80%
- 第3種(製造業など):70%
- 第4種(飲食店業など):60%
現在の税率は、店内飲食は10%、飲食料品の販売は軽減税率8%です。
以下、飲食店を例に本則課税と簡易課税の違いを具体的な数値で整理します。
| 項目 | 税抜額 | 税率 | 消費税 | 税込額 |
|---|---|---|---|---|
| 売上(店内飲食) | 1,000 | 10% | 100 | 1,100 |
| 仕入(飲食料品) | 400 | 8% | 32 | 432 |
| 経費(課税・光熱等) | 200 | 10% | 20 | 220 |
| 経費(非課税等・人件費等) | 300 | - | - | 300 |
【本則課税】
売上に係る消費税(仮受)=100
仕入・経費に係る消費税(仮払)=32+20=52
差引納付税額=100−52=48
【簡易課税(第4種・みなし仕入率60%)】
売上に係る消費税額=100
納付税額=100×(1−0.6)=40
本則課税では、実際の取引に含まれる消費税をもとに差額を計算し、その差額(上記では48)が事業者の納税額になります。
簡易課税は、実際の仕入や経費を使わないため、計算が簡単で事務負担を軽くできるというメリットがあります。一方で、実際の仕入割合によっては、納める消費税が実額より少なくなり、その分が手元に残る(いわゆる益税)こともあります。こうした特徴を理解したうえで、制度を選択することが大切です。
飲食料品卸売・小売・製造業のポイント
ここまでで、消費税の基本的な仕組みを確認しました。
では、もし飲食料品の税率が0%(免税・ゼロ税率)となった場合、実務上はどのような変化が起こるのでしょうか。
特に、飲食料品を扱う卸売業・小売業・製造業では、売上も仕入も消費税がかからなくなるため、これまでの課税計算とは構造が大きく変わります。
次に、具体的な数字を用いて、免税(ゼロ税率)となった場合の計算の流れを見ていきます。
| 項目 | 税抜 | 現在(軽減税率あり) | 免税(ゼロ税率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 消費税 | 税込 | 税率 | 消費税 | 税込 | ||
| 売上(飲食料品) | 1,000 | 8% | 80 | 1,080 | 0% | 0 | 1,000 |
| 仕入(飲食料品) | 600 | 8% | 48 | 648 | 0% | 0 | 600 |
| 経費(課税) | 100 | 10% | 10 | 110 | 10% | 10 | 110 |
| 経費(非課税等) | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 仕入・経費計 | 900 | - | 58 | 958 | - | 10 | 910 |
| 差引 | 100 | - | 22 | 122 | - | △10 | 90 |
表を見ると、現在では税込の「差引」が122、免税では90となっており、一見すると32の差があるように見えます。この差が、まさに消費税の影響です。
現在は、売上の消費税80から、仕入・経費の消費税(48+10)を差し引いた22を納税します。免税制度が導入されると、売上の消費税は0となり、仕入・経費に含まれる消費税(0+10)との差額−10、すなわち10が還付されることになります。したがって、税抜ベースでみれば、どちらも最終的な利益は100で一致します。
しかしながら、資金繰りの面では大きな違いが生じます。現行制度では、消費税分をいったん税込で受け取り、申告の際に納税する仕組みとなっており(中間納付が発生することもあります)、納付までの間は手元資金が多くなります。一方、免税制度では売上段階から税抜での受け取りとなるため、経費支払いの際に消費税分の負担が先行し、申告後に還付されるまでの間は資金繰りが厳しくなる可能性があります。課税期間を1か月や3か月に短縮すれば還付を早めることはできますが、その分、申告や会計処理の手間も増えます。
また、簡易課税制度を選択している事業者の場合は注意が必要です。簡易課税では、実際の仕入や経費を使わず、業種ごとの「みなし仕入率」に基づいて税額を計算するため、免税(ゼロ税率)となった場合でも還付を受けることができません。その結果、仕入や経費で支払った消費税分は戻ってこないことになります。
経理処理は簡易課税よりも煩雑になりますが、還付の可能性がある業種であれば、簡易課税のままにせず本則課税に切り替えることも検討すべきでしょう。制度変更が実務に与える影響は、こうした選択によっても大きく異なります。
飲食店のポイント
これまで見てきた卸売・小売・製造業とは異なり、飲食店の場合は少し事情が変わります。店内での飲食は現在10%の標準税率が適用されており、仕入となる飲食料品には軽減税率の8%がかかっています。このため、売上と仕入の税率が異なる構造になっており、免税(ゼロ税率)が導入された場合の影響も、他業種とは大きく異なります。
また、飲食店では、食材のほかにも光熱費や消耗品などの課税経費が多く、非課税である人件費の割合も大きくなりがちです。こうしたコスト構造の違いが、免税制度導入後の損益や資金繰りにどのように影響するかを整理してみましょう。
| 項目 | 税抜 | 現在(標準税率・軽減税率) | 免税(ゼロ税率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 消費税 | 税込 | 税率 | 消費税 | 税込 | ||
| 売上(店内飲食) | 1,000 | 10% | 100 | 1,100 | 10% | 100 | 1,100 |
| 仕入(飲食料品) | 400 | 8% | 32 | 432 | 0% | 0 | 400 |
| 経費(課税) | 200 | 10% | 20 | 220 | 10% | 20 | 220 |
| 経費(非課税等) | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 仕入・経費計 | 900 | - | 52 | 952 | - | 20 | 920 |
| 差引 | 100 | - | 48 | 148 | - | 80 | 180 |
先ほどの飲食料品卸売・小売・製造業とは異なり、飲食店の場合は、現行制度では「差引」が148、免税となると180となり、免税のほうが税込の差引金額が大きくなっています。これも、消費税の影響によるものです。
売上の消費税率は、現行制度でも免税となった場合でも10%のままですが、仕入となる飲食料品にかかる税率が8%から0%になるため、その分、見た目上の利益が大きくなっているように見えます。ただし、仕入にかかる消費税がなくなるということは、その分、仕入税額控除ができなくなることを意味します。結果として、消費税の納税後ベースで見れば、最終的な利益は一致します。
一方で、経営の現場では別の影響が生じる可能性があります。仮に、店内飲食は10%のまま、持ち帰りやデリバリー(いわゆる「中食」)が飲食料品として0%となった場合、同じ料理であっても税負担に差が生じることになります。消費者の価格感覚としては、持ち帰りやデリバリーのほうが割安に見えやすく、価格競争の面では店内飲食が相対的に不利になりやすい構造となります。
その結果、飲食店においては、持ち帰りやデリバリーへの対応を強化する、あるいは店内飲食については「場所」「接客」「雰囲気」など、食事そのもの以外の付加価値を高め、サービス業としての強みをより前面に出していくといった経営判断を迫られる可能性があります。税制が、事実上、業態や提供方法の選択に影響を与える点は、実務上も無視できないポイントといえるでしょう。
さらに、簡易課税制度を選択している飲食店の場合は、少し状況が異なります。簡易課税では、消費税の納税額を「売上高」に基づいて計算するため、実際の仕入や経費の内容は反映されません。仮に仕入が免税(ゼロ税率)となったとしても、みなし仕入率が現行のままであれば、従来と同じ計算方法が適用されることになり、結果として現在より有利になる可能性も考えられます。
もっとも、こうした制度上のバランスを調整するため、飲食店の「みなし仕入率」が見直される可能性も十分にあります。免税(ゼロ税率)導入の有無だけでなく、その際に簡易課税制度がどのように扱われるのかについても、今後の制度設計や国税庁からの発表を注視していく必要があるでしょう。
まとめ
今回のように、飲食料品を消費税の対象外(免税・ゼロ税率)とする方針は、家計支援という面では分かりやすい一方で、事業者にとっては実務や経営判断に影響を及ぼす可能性があります。
卸売・小売・製造業では、課税方式によっては還付が生じる一方、飲食店では仕入税額控除ができなくなることで、見た目上の利益や納税額の構造が変わります。特に、店内飲食は10%のまま、持ち帰りやデリバリー(中食)が0%となる場合には、価格の見え方に差が生じ、経営戦略や業態選択に影響を与えることも考えられます。
また、簡易課税制度を選択している事業者では、免税(ゼロ税率)が導入された場合に一見有利に見える場面も想定されますが、その場合には、みなし仕入率の見直しなどが行われる可能性もあります。現行制度だけを前提とした判断には注意が必要でしょう。
もっとも、今回示されている内容は、あくまで検討段階のものであり、制度の導入や具体的な設計が決まったわけではありません。現時点で慌てて対応する必要はありませんが、今後の議論の動向を注視しつつ、自社の取引内容や課税方式がどのような影響を受けるのかを把握しておくことが、実務上は重要といえます。
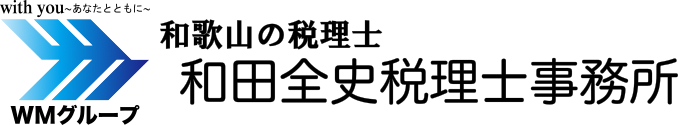

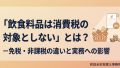
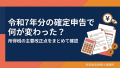
コメント