和歌山の税理士、和田全史です。いつも当ブログをお読みいただきありがとうございます。これまで「iDeCoの基本」と「制度比較」を解説してきましたが、いよいよ今回は「出口戦略」のお話です。一時金と年金、どちらを選ぶか――答えは一つではありません。税制上の控除の仕組みや受け取りのタイミングによって、手取り額は大きく変わります。
近年の制度改正では、受給開始年齢の上限が70歳から75歳へ延長され、それに合わせて会社退職金とiDeCo一時金の調整期間が14年から19年へ拡大されました。さらに、「5年ルール」が「10年ルール」へ見直される改正も決定しており、2026年以降の受給から適用されます。受け取りの順番や組み合わせ方によって、これらのルールがどう適用されるかが変わるため、出口戦略の設計がより重要になってきています。
本記事では、こうした最新制度を踏まえながら、一時金・年金・併用の違い、税制優遇の仕組み、そして実務上の注意点を整理していきます。
1. iDeCoの出口戦略とは?
iDeCoは「掛金を拠出して節税しながら資産を積み立てる制度」として知られていますが、拠出が終わった後にどう受け取るかで、最終的な手取り額が大きく変わります。これを、金融機関や専門家の解説などでもよく使われる表現で、「出口戦略」と呼ぶことがあります。
出口戦略には、大きく分けて次の3つの選択肢があります。
- 一時金で受け取る
- 年金で受け取る
- 一部を一時金・残りを年金で受け取る(併用)
単純な二択ではなく、控除制度と受け取り時期の組み合わせ次第で最適解が変わるのが特徴です。
2. 一時金受取の特徴と税制
iDeCoを一括で受け取る場合、その給付は「退職所得」として扱われます。退職所得には大きな税制上の優遇があり、退職所得控除と1/2課税の仕組みが適用されます。
退職所得控除とiDeCoの「加入年数」
退職所得控除は、原則として勤続年数に応じて計算されます。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
iDeCoの場合は会社の勤続年数ではなく、iDeCoの加入年数を用いて控除を計算します。加入期間が長いほど控除額は大きくなり、税負担は軽減されます。
控除額を差し引いた残りの金額をさらに1/2にして課税所得とするため、給与所得などに比べて大きく税負担が軽くなるのが特徴です。
同じ年に受け取る場合
会社退職金や小規模企業共済の一時金など、同じ「退職所得」に分類される給付と同じ年に受け取った場合は、合算して1つの退職所得として計算されます。その合算額に対して、勤続年数(iDeCoは加入年数を用いる)を基に算出した退職所得控除を差し引き、残りを2分の1にして課税所得とします。
別の年に受け取る場合(19年ルールと10年ルール)
iDeCo一時金と退職金を別の年に受け取る場合は、それぞれ独立して退職所得を計算します。ただし、退職所得控除を二重に使えないように調整するルールがあります。
- 退職金が先 → iDeCoが後の場合
退職金を受けた年の「前年以前19年以内」に受けたiDeCo一時金は、勤続年数が調整されます。(条文通り「前年以前19年以内」で、俗称もそのまま「19年ルール」と呼ばれています。) - iDeCoが先 → 退職金が後の場合
従来は「前年以前4年以内」に受け取った場合に調整が必要でしたが、令和7年度税制改正により「前年以前9年以内」に拡大され、2026年以降は10年ルールとして適用されます。(俗に「10年ルール」と呼ばれますが、条文上は「前年以前9年以内」と表記されているため、呼び方と数字にズレがあります。)
俗称と条文表現の違い
「10年ルール」=条文上は「前年以前9年以内」だが、退職金を受けた年を含めてトータル10年間カバーするためそう呼ばれている。
「19年ルール」=条文通り「前年以前19年以内」と表記されており、そのまま「19年ルール」と呼ばれている。
別の年に受け取る場合には、10年ルールや19年ルールで控除の調整が入ります。詳細な計算方法は複雑なのでここでは省略しますが、制度上は控除を二重に使えない仕組みになっています。
3. 年金受取の特徴と税制
iDeCoを分割して受け取る場合は、「公的年金等の雑所得」として課税されます。ここで重要になるのが公的年金等控除です。
公的年金等控除の最低額(通常)
- 65歳未満:60万円
- 65歳以上:110万円
ほとんどの方はこの水準で控除が計算されますが、給与や事業所得などのその他の所得が極端に多い場合は、次のように引き下げられます。
- その他の所得が1,000万円超:50万円(65歳未満)、100万円(65歳以上)
- その他の所得が2,000万円超:40万円(65歳未満)、90万円(65歳以上)
公的年金等控除は「1人につき1つ」であり、国民年金・厚生年金とiDeCo年金を合算して適用します。控除額以下であれば課税は発生せず、超えた部分のみが雑所得として課税されます。
4. 併用(年金+一時金)のパターン
iDeCoの受け取りは「一時金」か「年金」だけではなく、一部を一時金・残りを年金で受け取る併用方式を選ぶことも可能です。多くの金融機関がこの方法を提供しており、出口戦略の柔軟性が高まります。
- 併用のメリット
- 退職所得控除と公的年金等控除を両方活用できる
- 税負担を平準化できる
- 生活設計に合わせられる
- 併用の注意点
- 金融機関による制限(回数・期間・頻度など)
- 退職金や他の年金との調整が必要
- 設計次第で手取りが大きく変わるためシミュレーションが不可欠
5. まとめ(出口戦略の考え方)
iDeCoの受け取り方は、大きく分けて「一時金」「年金」「併用」の3種類があります。どの方法を選ぶかによって、最終的な手取り額は大きく変わります。
- 一時金(単独で受け取る):加入年数に応じた控除で有利になりやすい
- 一時金(他の退職金と重なる):同年なら合算、別年でも10年ルールや19年ルールで調整され、単独受給より課税されやすい
- 年金受取:公的年金等控除が使えるが、他の年金収入が多い人には不利になり得る
- 併用:一時金と年金の控除を両方活用でき、課税分散と資金計画の両立が可能
出口戦略は「いつ・どのように」受け取るかで有利不利が変わります。最適解は退職金・年金収入・他の所得との兼ね合いによって異なるため、具体的な設計を検討する際には、早めに専門家に相談することをおすすめします。
次回は「iDeCo活用術:リスク管理とリバランス戦略」と題して、積み立てた資産をどのように運用・調整していくかについて解説します。出口戦略とあわせて考えることで、長期的により安定した資産形成につなげることができます。
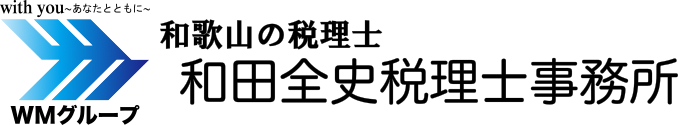
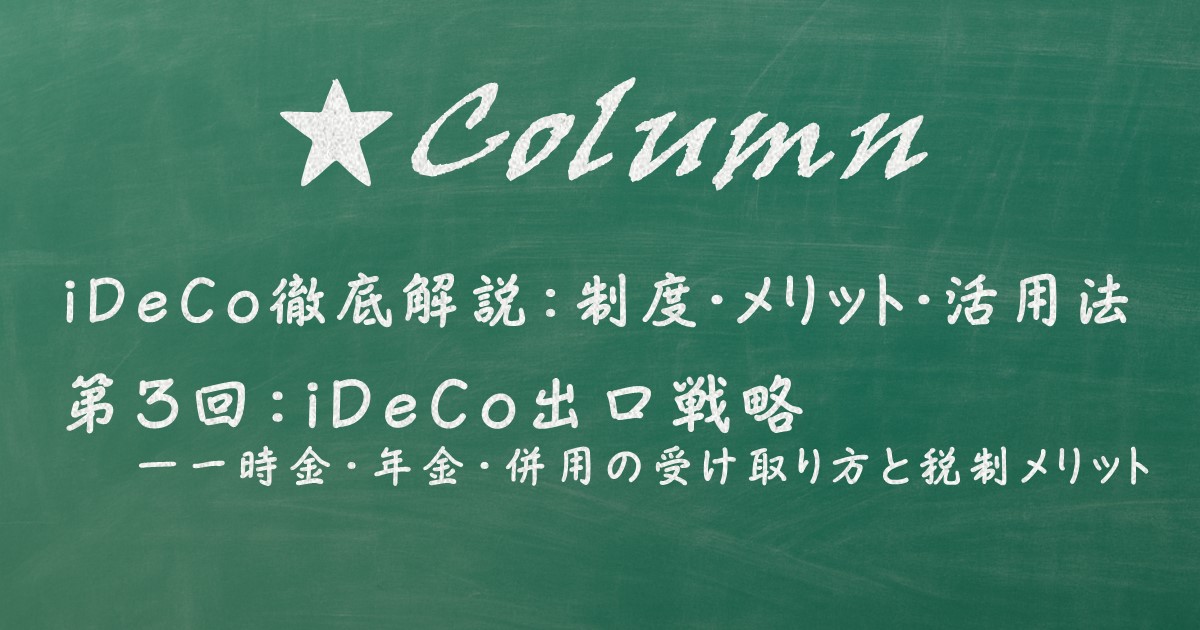

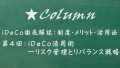
コメント